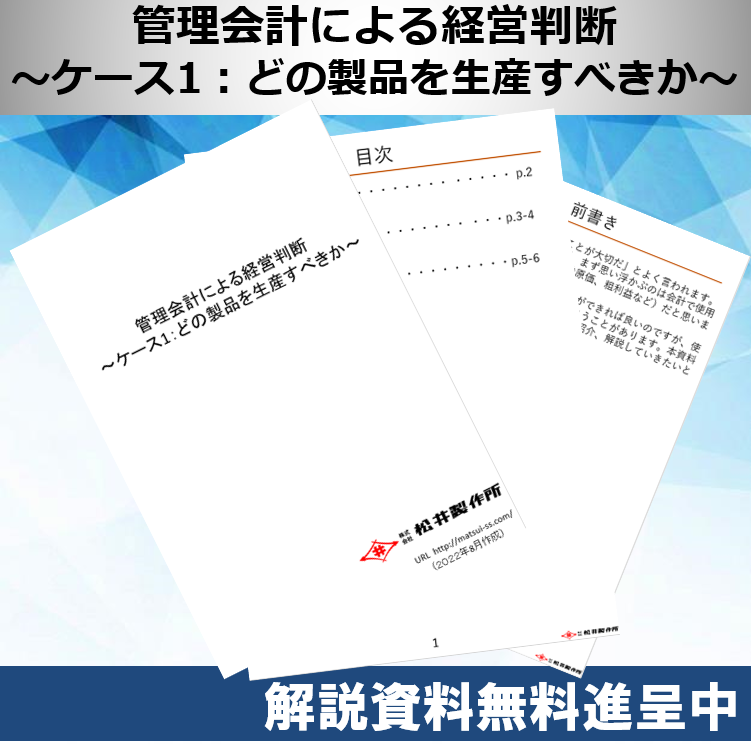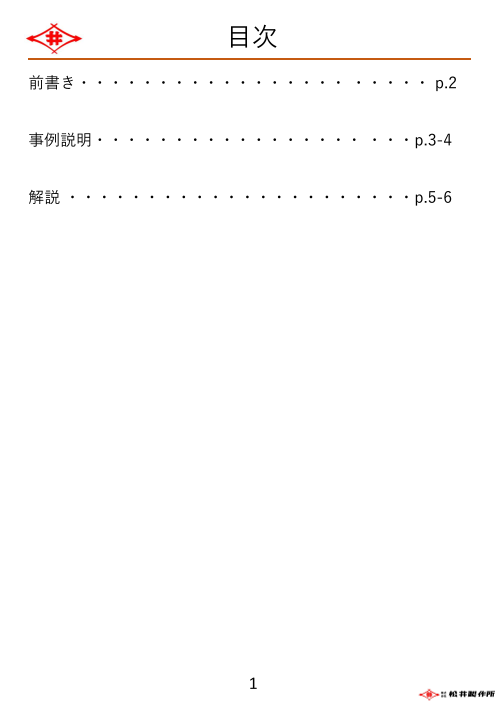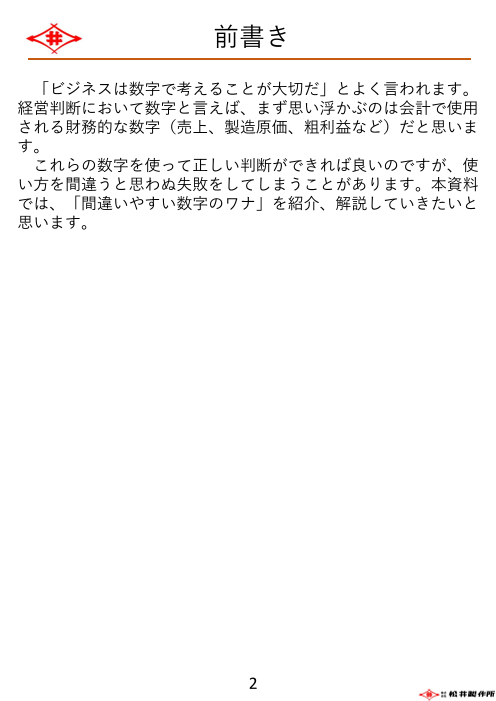1/7ページ
ダウンロード(895.3Kb)
会計の数字を正しく使って経営判断に活かすための注意点を解説します!
「ビジネスは数字で考えることが大切だ」とよく言われます。
経営判断において数字と言えば、まず思い浮かぶのは会計で使用される財務的な数字(売上、製造原価、粗利益など)だと思います。
これらの数字を使って正しい判断ができれば良いのですが、使い方を間違うと思わぬ失敗をしてしまうことがあります。本資料では、「間違いやすい数字のワナ」を紹介、解説していきたいと思います。
このカタログについて
| ドキュメント名 | 管理会計による経営判断~ケース1:どの製品を生産すべきか~ |
|---|---|
| ドキュメント種別 | 事例紹介 |
| ファイルサイズ | 895.3Kb |
| 取り扱い企業 | 株式会社松井製作所 (この企業の取り扱いカタログ一覧) |
この企業の関連カタログ

このカタログの内容
Page1
管理会計による経営判断
~ケース1:どの製品を生産すべきか~
URL http://matsui-ss.com/
(2022年8月作成)
Page2
目次
前書き・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ p.2
事例説明・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.3-4
解説・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・p.5-6
1
Page3
前書き
「ビジネスは数字で考えることが大切だ」とよく言われます。
経営判断において数字と言えば、まず思い浮かぶのは会計で使用
される財務的な数字(売上、製造原価、粗利益など)だと思いま
す。
これらの数字を使って正しい判断ができれば良いのですが、使
い方を間違うと思わぬ失敗をしてしまうことがあります。本資料
では、「間違いやすい数字のワナ」を紹介、解説していきたいと
思います。
2
Page4
事例説明
ある会社では、製品Aと製品Bの2種類の製品を生産している。ど
ちらも同じ機械を使用し、作る手間も同じとする。現在の製品情報
は以下表1のとおりとする。
【表1】x月の損益計算書
(円)(※“生産販売量”のみ(個))
一個当たり 一個当たり 生産販売
製品 売価 製造原価 販管費 純利益
総原価 利益 数量
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ=Ⓑ+Ⓒ Ⓔ=Ⓐ-Ⓓ Ⓕ Ⓖ=Ⓔ×Ⓕ
A 1,200 940 170 1,110 90 100 9,000
B 1,800 1,540 220 1,760 40 100 4,000
計 13,000
製造原価内訳
(円)
製品 変動費 固定費 計
A 700 240 940
B 1,200 340 1,540
この数字を見た社長が、次の様な判断をしたとする。
「製品Aの方が利益が大きいのだから、次月は製品Aだけを作ろう!」
(【表2】参考)
このとき、次月の損益計算書はどのようになるだろうか?
(※会社の機械台数や人数などの条件は変わらないとする)
【表2】x+1月の計画
一個当たり 一個当たり 生産販売
製品 売価 純利益
総原価 利益 数量
A 1,200 1,110 90 100 9,000
B 1,800 1,760 40 100 4,000
計 13,000
新計画 A 1,200 1,110 90 200 18,000
3
Page5
事例説明
しかし、実際のx+1月の損益計算書は以下表3のとおりとなった。
【表3】x+1月の損益計算書 (円)(※“生産販売量”のみ(個))
一個当た 一個当たり 生産販売
製品 売価 製造原価 販管費 純利益
り総原価 利益 数量
A 1,200 990 195 1,185 15 200 3,000
X月の18,000円から3,000円
製造原価内訳 (円) (▲15,000円)と、大幅に利益が
減少した。
やけを起こした社長は、反対にx+2月は製品Bだけを生産、販売した。
その結果を以下表4に示す。
【表4】x+2月の損益計算書 (円)(※“生産販売量”のみ(個))
一個当た 一個当たり 生産販売
製品 売価 製造原価 販管費 純利益
り総原価 利益 数量
B 1,800 1,490 195 1,685 115 200 23,000
X月の18,000円から23,000円
製造原価内訳 (円)
製品 変動費 固定費 計 (+5,000円)と、利益が増加した。
B 1,200 290 1,490
社長は、いったい何がどうなっているのかと混乱した・・・
考え方が間違っていた
(次ページから解説)
4
Page6
解説
なぜこのようなことが起こるのかというと、製造原価のうちの“固定
費”、及び“販管費”(これも固定費の一種)の配賦が原因である。企
業で一般的に使用される財務会計では、固定費は製品などに配賦さ
れることとなっている。
【表1】、【表3】、【表4】の“固定費”と“販管費”を比べると、異なる値と
なっている。
しかし、それぞれの合計額は以下の計算の様に同額となっている。
【表1】の”固定費”合計額:240円×100+340円×100=58,000円
【表1】の“販管費”合計額:170円×100+220円×100=39,000円
【表3】の”固定費”合計額:290円×200=58,000円
【表3】の“販管費”合計額:195円×200=39,000円
【表4】の”固定費”合計額:290円×200=58,000円
【表4】の“販管費”合計額:195円×200=39,000円
【表1】では、 ”固定費”合計額と“販管費”合計額が製品A,製品Bそれ
ぞれに何らかの方法に従って配賦されていた。製品Bの生産を止め
たところで、工場全体での固定費の金額は変わらない。よって、【表
3】では生産Aのみを生産したことによって、従来製品Bに配賦されて
いた分の固定費も製品Aに配賦されることになった。このことが判断
を誤った原因である。
製品に固定費を配賦しない会計計算手法として、“直接原価計算
“がある。”直接原価計算”では利益を「売価-変動費(=貢献利益)」
として計算する。なぜ“貢献利益”と呼ぶかというと、固定費の回収に
貢献するからである。
5
Page7
解説
直接原価会計に従った方法で最初から計算していたらどの様な結
果だったか見てみる。
再掲:【表1】x月の損益計算書
(円)(※“生産販売量”のみ(個))
一個当たり 一個当たり 生産販売
製品 売価 製造原価 販管費 純利益
総原価 利益 数量
Ⓐ Ⓑ Ⓒ Ⓓ=Ⓑ+Ⓒ Ⓔ=Ⓐ-Ⓓ Ⓕ Ⓖ=Ⓔ×Ⓕ
A 1,200 940 170 1,110 90 100 9,000
B 1,800 1,540 220 1,760 40 100 4,000
計 13,000
製造原価内訳 (円)
まず、売価と変動費に注目して、製品A,製品Bそれぞれの貢献利益
を計算する。
製品Aの貢献利益:1200-700=500円
製品Bの貢献利益:1800-1200=600円
製品Bの貢献利益の方が大きい結果となった。
よって、固定費合計額(”固定費”合計額:58,000円+“販管費”合計
額:39,000円=97,000円)を回収するのに製品A,製品Bのどちらを製
造・販売した方が良いかというと、製品Bとなる。
この様に、直接原価会計を用いると判断を間違えにくい。
¥ 貢献利益
固定費
販売数
6